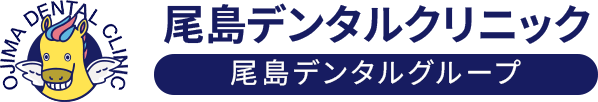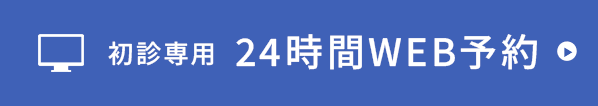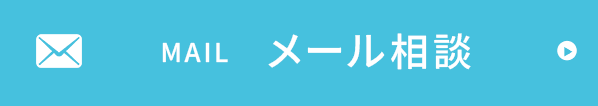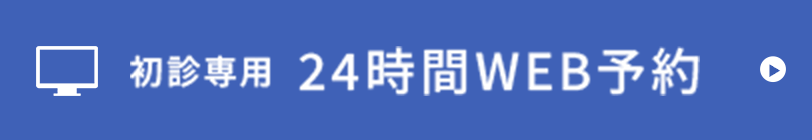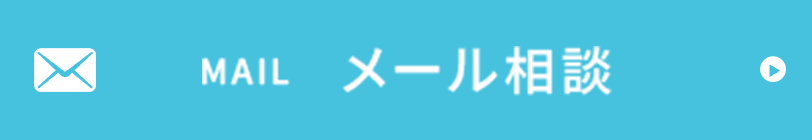2020年08月24日
こんにちは、歯科医師の伊藤です。
コロナウィルス感染拡大の影響でテレワークやオンラインでの会議やセミナーが定着してきています。
歯科業界も同じく、セミナーや業者の方々とのやりとりはオンラインで行う機会がとても増えました。
最初はオンラインでのやりとりに戸惑いも感じましたが、慣れてくると良い点もたくさんみえてきます。
オンラインのメリットは何より遠隔で繋がれるという点です。
群馬と東京もすぐ繋ぐことができ、今まで1時間以上かけていた移動時間がゼロになります。
オンラインでのやりとりが益々定着してきたら人の動きはかなり少なくなってくるのではないでしょうか。
尾島デンタルクリニックでは、患者さんとの相談もオンラインでできるようにシステムを整えていきたいと考えております。
遠方から来院したいけど移動が大変だったり、時間に制限がある方などがオンラインでご自宅で相談できるようになると患者さんの負担も軽減できるのではないかと考えております。
通って頂ける患者さんにより通いやすい歯科医院になれるよう取り組んで参りますので今後ともよろしくお願い致します。
2020年08月11日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
暑い日がつづいていますね。
体調を崩さないように、水分補給は定期的に行うようにしましょう。
さて、今回は根の治療についてお話をさせていただきます。
一度、神経の治療をして、再度根の先に膿の袋ができてしまった場合…
再度、根の治療を行う必要があります。
根の治療を始めていくと、ときに患者さんから「すでにこの歯は神経がなくなっているのに、どうして管の中を触られると痛むのですか」と尋ねられることがあります。
質問にお答えすると、この原因は何種類かあります。
①根の先の穴から感染した歯茎の組織が管の中に入り込んでいる感染した歯茎の組織に痛覚が残っているため、器具で触った際に痛みが出ます。
②根の先まで器具が到達したときの圧圧を感じることで歯の周囲に痛みを感じることがあります。
③根の先から器具の先が出る
根の先まで器具が到達し、先端の組織と触れることで痛みが出ることがあります。
④前回の治療で、神経が先に残っている可能性としては低いですが、時に神経の一部が残っていて、触れたときに痛みが出ることがあります。
上記のように、いくつか原因がありましたが、痛みの回避のために、治療前に麻酔を行うことをおすすめしております。
痛みが苦手な方がいらっしゃいましたら、治療前にお気軽にお声がけください。
2020年08月6日
こんにちは、歯科医師伊藤です。
いつも尾島デンタルクリニックにご来院頂きありがとうございます。
来院して頂く患者さんの中には「他の医院で歯を抜かなければいけないと言われたので来院した」とおっしゃる方がいます。
歯を抜かなければいけない状況には何通りかパターンがあります。
重度の歯周病や虫歯、歯が割れているなどがよくあるもので、状況によっては抜歯を回避できるケースもあります。
抜かなければいけない歯を無理やり残すとそこから問題が大きくなることもあるので、抜歯をした方が良いことも当然あります。
そのため一概に歯を残すことが良いことではない場合もあります。
しかし、誰もが自分の歯を少しでも長持ちさせたいというお気持ちがあるはずです。
当院では歯科医師がしっかりとその歯の状況を診査診断し、抜かなくても済むのか、やはり抜いた方が良いのかを詳しく説明致します。
残せる方法がある場合は適切な対処を行い、一方的に抜歯をすることはありません。
歯周病治療なども含めて経験豊富な歯科医師も多数在籍しておりますので、お悩みの方や相談をしたい方は是非一度ご来院下さい。
皆様のお力になれればと考えております。
2020年07月29日
クーラーの活躍する季節となりましたが、みなさん体調はいかがですか。
しっかり水分をとって熱中症には気を付けましょう。
以前、痛くないむし歯についてお話ししましたが、今回は逆に、歯が痛いのにむし歯でない場合についてお話します。
歯が痛い、と思ったら原因はむし歯か、知覚過敏か、歯周病か、いずれにせよ歯に原因があると思ってしまいがちですが、全く歯には異常がないのに痛みが出る場合もあります
それを「非歯原性歯痛」といいます。
この場合、歯科治療を行っても痛みはなくなりません。
その原疾患から以下の8つに分けられます。
① 筋・筋膜性歯痛
歯が原因でない歯痛の原因として最も多いのが咀嚼筋などの疲労により生じる筋・筋膜性歯痛です。原因の筋を圧迫することで歯に痛みが生じます。
② 神経障害性歯痛
帯状疱疹などのウイルス性の疾患によってウイルスが歯の神経の近くに達すると歯の痛みを感じることがあります。
③ 神経血管性歯痛
片頭痛、群発頭痛が原因として多く、その場合、上の奥歯に痛みを生じます。
④ 上顎洞性歯痛
上顎洞炎や、上顎洞悪性腫瘍などが原因になることもあります。
⑤ 心臓性歯痛
狭心症、心筋梗塞などの関連痛が歯に生じることもあります。
⑥ 精神疾患または心理社会的要因による歯痛
統合失調症や大うつ病性障害などが原因の場合です。
⑦ 特発性歯痛
不眠症の人はからだに痛みを感じることが多いとされます。痛みのある部位に異常がなく、多くの場合他の部位にも頭痛や腰痛など慢性的な痛みを伴っています。
⑧ その他
歯が痛いのに歯が原因じゃないなんて、と意外に思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。上記の場合は、いずれも歯科医院でなく、他科の病院による原疾患の治療が必要になりますので、必要に応じて紹介状を書かせていただきます。
気になることがありましたらいつでもご気軽にご相談ください。
2020年07月17日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
コロナ感染者が増えてきて生活は息苦しく、身の心もすり減ってきますね、、、しかしこんな時こそ気持ちはしっかり持って下を向かずに日々過ごして行きましょう!病は気から!気持ちが大切です!!
さて、本日は当院が行なっている
『セカンドコンサル』
についてお話します。
以前も一度お話しましたが、コンサルとは、当院と患者様の間で行われる意見交換のようなものです。当院からは、当院の行なっている取り組みや治療法の説明などの情報提供を行い、患者様からはどこが痛いのか?何に悩んでいるのか?不安はあるか?などをお聞きしていきます。
セカンドコンサル?ってことはファーストコンサルは何?と思う方もいるかと思います。
ファーストコンサルは、初診時に行うコンサル(問診)のことです。
ここでは、当院の取り組みの説明や患者様の主訴(一番気になっているところ)、全身状態の確認などをメインに行っています。
こちらは当院に初めていらっしゃった方や1年以上期間が空いた方が対象となります。
では、セカンドコンサルとは何か。
セカンドコンサルは、お口の中に治療しなくてはいけない部分が多い方、治療するかどうか迷う方、矯正やインプラントなどの治療が必要な方などを対象に行うコンサルで、簡単に言うと、これからお口の中をどうしていきたいか?の相談を行います。
・治療が必要な部位の確認
・親知らず抜歯する?そのままにする?
・歯が抜けたままのところはどうする?
・銀歯を白くしたい?
・歯並び気になっていますか?
・費用の相談
・治療期間の相談
などなど、お口の中の問題点について、しっかりと時間をとって患者様にとって一番良いと思われる治療方法を一緒に考えていきます。
セカンドコンサルは、専門のスタッフも担当させていただきますので、普段なかなか先生には言えないような悩みや希望があれば遠慮なくご相談ください。
お口の中はその人ごとに様々で、またその人の生活や仕事、価値観、時間的背景、費用的背景などによって考えて方もたくさんあります。
何が一番良い治療なのかを一緒に探していきましょう。
2020年07月13日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
雨の多い季節になってきましたね。
突然の雨に、対応できるように天気予報の確認は毎朝行うようにしましょう。
以前、私がマウスピース矯正をしているお話をさせていただいたことをおぼえていますでしょうか。
時間が経つのは早いもので、私がマウスピース矯正を始めて、1年近くが経ちました。
今のところ、トラブルなくマウスピース矯正生活を送ることができています。
そこで、今回はマウスピース矯正生活を送るうえで、私が気を付けていることを話させていただきます。
① 食事時間以外はマウスピースをつける
外食時や旅行の際は、外している時間が長くなることが多いのですが、食後にはすぐ装着するように心がけています。
ときには、歯磨きができない場面もありますよね。歯磨きができていないのでマウスピースを装着しないかたもいるかもしれません。
しかし、マウスピースを外している時間が長いと、歯はすぐに元の位置に戻ろうとしてしまいます。なので、わたしは、多少の気持ち悪さを実感しつつ、そのまま装着し、歯磨きができるときに、徹底的に磨いています(マウスピースにも汚れがついているので洗浄を行います)。
② マウスピースを付けた際にはチューイを噛む
マウスピースを装着する際には、ある程度装着後にチューイというゴムを噛んでしっかり装着を行います。
この操作を行うか、行わないかで大きく矯正治療の結果に差が出てしまいます。
チューイを噛まないで、マウスピースを入れた場合、自分では装着できていると思っていても、多少浮いていることがあります。このまま装着を続けていても、適切な力がはに加わらず、予定していた位置に歯が動かず、次回以降のマウスピースが合わなくなることがあります。
③ マウスピースをつけている間は水を飲む
マウスピースを装着しているときに、お茶、コーヒーを飲むとマウスピースに色がついてしまいます。また、ジュースなどの砂糖が含まれているものを飲むと、歯とマウスピースの間に砂糖が入り込み、むし歯になりやすくなってしまいます。
飲食はマウスピースを外した際に思う存分に楽しむようにしましょう。
今回は3つほど、気を付けていることをお話しさせていただきました。
そのほかにもいくつかありますが、また今度お話をさせていただきたいと思います。
マウスピース矯正に少しでも興味がある方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
👉 大人の矯正治療について
👉 お子様の矯正治療について
2020年07月3日
こんにちは、歯科医師の今野です。
今日は「痛くないむし歯」についてお話します。
私たちが患者さんに治療予定のむし歯についてお話しするとき、患者さんが分かりやすいように治療部位の写真を撮ってお見せするのですが、お見せしたときに
「そんなことになっていたなんて」
「痛くないから、むし歯じゃないと思ってた…」
とおっしゃる方がよくいらっしゃいます。
また、
「2週間前までむし歯が痛かったが、放っておいたら治った」
とおっしゃる方もいらっしゃいますが、痛みが引いたからといって、むし歯自体が治ったわけではありません。
では、むし歯で痛みの出ない場合とはどのような状況なのでしょうか。
むし歯で痛みのない場合
1、 むし歯が小さいとき(初期むし歯)
むし歯がまだ小さくてエナメル質、という歯の表層部分にとどまっている場合はまだ痛みが出ません。この段階ならまだ、予防管理を行うことで削らずに済む場合があります。
2、 むし歯が神経近くまで進んでいるが痛みがないとき
むし歯が神経の近くまで進んでいて痛みのない場合は、むし歯がゆっくり進行している時です。むし歯がゆっくり進むにつれて神経を保護するように歯の内側に硬い組織(第三象牙質)が作られるので、痛みのないまま進行します。
放っておくと、気づかぬうちにむし歯が神経に達し、神経をとる処置が必要になりますので、早期の治療が必要です。
3、 神経が死んでしまっているとき
むし歯が神経のお部屋まで到達しているのに痛みのない場合、歯の神経が死んでしまっている可能性があります。
一度痛みが出たのに治った、と思っている場合はこれが該当する可能性があります。ここまでむし歯が進んでしまっていると、歯の根の先に膿がたまっていることが多く、そこから歯の埋まっている骨が溶かされて歯が揺れてきたり抜歯になってしまうこともあるので、痛くなくても早めの受診が必要です。
削られた歯、抜けてしまった歯は、人工物で補うことはできても自分自身の歯を再生することは現段階ではできません。
ご自身の大切な歯を守るためには、痛みがなくても定期的に歯科医院を受診し、予防管理を行うことが大切です。
2020年06月27日
こんにちは、歯科医師の嶋崎です。
だんだんとあったかくなってきましたね。
気温の変化に関係なく、手洗いうがいなどの感染対策は日々行いましょう。
さて、本日は、子どもの歯磨きについてお話をしようと思います。
お子さんの中には、歯磨きを嫌がる子もいますよね。
かといって、歯磨きをしないわけにはいきません。
基本的に、子どもが歯磨きを嫌がる理由は「こわい」、「いたい」、「ねむい」などがあります。
「いたい」に関しては、
① 歯ブラシのブラッシング圧が強い
② 歯ブラシを大きく動かしすぎている
③ 上唇小帯を指でカバーしていない
などの原因が考えられます。
また、お子さんが歯磨きを嫌がることにより、自分の歯ブラシが下手なせいだと思ってしまい、おそるおそる歯磨きを行うと、自信のなさが子どもに伝わり、より歯磨きを嫌がってしまうことがあります。
お口の中は、体の中でもとくに敏感な部分です。
歯磨きを嫌がるお子さんには、歯磨き前に顔や歯茎を優しく指で触れて、リラックスをした状態で歯磨きを始めましょう。
お子さんに優しい声掛けをしながら、時には歌いながら笑顔で歯磨きを行い、楽しい雰囲気を作り出し、お父さんお母さんが歯磨きを楽しんでいる姿をお子さんに見せることが、歯磨きを、嫌なものから楽しいものへ変えるきっかけになっていきます。
また、お子さんが大きくなってくると、自分で歯磨きを行うようになり、仕上げ磨きを行わなくなる傾向があります。
しかし、子どもの小さな手では歯ブラシをうまく動かすことは難しく、上手く磨けていないことがほとんどです。
むし歯や歯肉炎にならないためにも、10~12歳位までは、必ず仕上げ磨きを行うようにしましょう。
歯磨きの仕方でわからないことがあれば、ご気軽にご相談ください。
2020年06月18日
こんにちは、歯科医師伊藤です。
全国的な新型コロナウィルスの感染拡大も落ち着いてきましたが、以前より歯科医院でも感染予防対策に力を入れております。
当院では感染拡大前から院内感染予防のため、消毒滅菌の取り組みに力を入れてきました。
日頃から消毒滅菌に関するミーティングを開き、院内システムの改良を繰り返して来ました。
今回のコロナウィルスの感染拡大を受け、より一層感染予防の意識を高め、スタッフ一丸となって安全な歯科医院を運営できるよう日々取り組んでおります。
器具の個別滅菌はもちろんのこと、一人一人使い捨てできるディスポーザブル器具の使用、診療台の毎回清掃、全スタッフのマスク、フェイスシールドの常時着用、スタッフの手指消毒、換気、清潔域不潔域の分離など様々な対策を実施しています。
安全な歯科医院を目指し、皆様に安心して通院して頂けるようこれからも全力を尽くして行きたいと考えております。
今私達に出来ることは、院内でできる感染予防をしっかりと行っていくことと適切な歯科治療を提供することです。
皆様にもご協力頂き、治療前の問診票やマスクの着用、待合室の制限などをお願いしているのも対策の一つです。
お手数おかけしますが、ご協力頂けると幸いです。
2020年06月8日
歯磨きについて
こんにちは、歯科医師の菅原です。
まだまだコロナで大変ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?
今まで僕は歯周病の話をしてきて歯周病の怖さやどの様な病気かわかっていただけたと思います。
今日は歯磨きの話です。
まず根本的な話ですが、歯磨きは口腔内の汚れを取るために行います。
口の中に汚れがあると早くて3日ぐらいでむし歯になると言われています。
むし歯になってからだと歯は、2度とむし歯前の状態に戻ることはないので、まずしっかり歯磨きをするということが歯科治療で大切です。
「むし歯になるの3日かかるならそんなに頻繁に磨かなくても良いじゃん」、て思う方もいるかもしれないですが、それは違います。
歯磨きはどんなにうまい人でも15%から20%の磨き残しがあると言われています。
毎回100%でやっても汚れが残っていることがあると言うことです。
要するに、1日3回の歯磨きを一生懸命やる事で限りなく汚れを0に近づけることが目標な訳です。
汚れをしっかり落とすためには、汚れが何処に溜まりやすいか知っている事も大切です。
汚れが残りやすい場所は歯の溝の部分、歯と歯の間、歯と歯茎の間です。
また患者さんそれぞれで汚れやすい場所も違うので、それぞれ衛生士が指導して行きます。
この汚れやすい場所を意識して磨きます。
そして歯ブラシだけでは、歯と歯の間の部分は磨き残しが多くなるのでしっかりフロスを使いましょう。
歯磨きは歯科治療の基本なので皆さん頑張って行なっていきましょう。
歯磨きの詳しい方法などを知りたい人がいらっしゃいましたら、当院の歯科医師、スタッフに遠慮なく聞いて下さい。