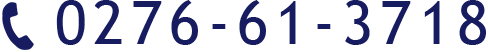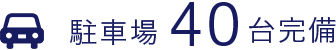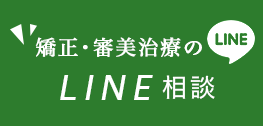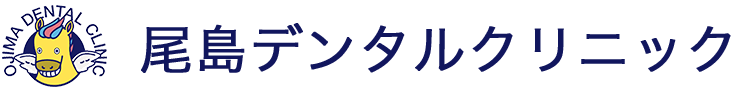2025年01月27日
こんにちは。歯科医師の大藤です。
歯科治療で詰め物や被せ物で使用される素材として主に金属、セラミック、コンポジットレジンと呼ばれる樹脂が挙げられます。
この中でも、『見た目が良いだけじゃないんですか?』と良く聞かれる、セラミックの特徴についてご紹介しようと思います。
セラミックを入れた芸能人や有名人の方や、セラミックでピカピカに真っ白になった前歯など、色々なイメージがあると思いますが、どんな性質や特徴があるかご存知でしょうか?
まず、そもそもどんな時にセラミックを用いた治療が必要になるのか?ということについてですが、
・虫歯で歯の一部が失われた時の修復
・根の治療後に被せ物が必要になった時
・歯の変色や金属の修復物を審美的改善のためにやりかえる時
・金属アレルギーがあり口腔内に金属を入れられない時
・セラミック矯正(当院では行っていません)
など、治療の幅は幅広くあります。
セラミックの特徴は、簡潔に言いますと陶製の白い材料で、審美性が良く口腔や生体への親和性が高い材料です。
抽象的な表現ですので、詳しくご紹介してきますね。
まず見た目に関してですが、セラミックは天然の歯と同じような透明感や細かい濃淡まで再現できるため、極めて歯に近い美しい見た目で仕上げることができます。
私たち歯科医師でも、肉眼では天然の歯と見分けがつかないようなリアルな見た目に仕上げることができます。
(時折、有名人の方などで蛍光色の様な真っ白な前歯をお見かけしますが、当院での治療は周囲の歯と調和の取れた自然な色調で治療をご提案しています。)
また、天然の歯は食べ物や飲み物の色素が沈着し、段々と着色してきますが、セラミックは着色しにくい素材のため、白さを長く維持することができます。
これに対して、金属を使った銀歯は、金属が溶け出し、歯や歯茎が黒ずんだり着色することがあり、完全に着色を落とすことは難しくなります。
また、樹脂の材料はタッパーの様に色を吸収する性質があり、一度色がついてしまうと詰め替える以外に改善が難しくなります。
次にご紹介するのは、金属などに対して虫歯になりにくいという特徴で、一番大きな特徴です。
金属は、温度によって微量に膨張収縮をします。
これにより接着剤の劣化や溶出を招き、歯と隙間ができるため虫歯が再発しやすくなります。
これに対してセラミックは長期にわたって変形がほぼないため、歯と一体化した状態が保たれ虫歯が再発しにくいと言われています。
また、樹脂の材料は強度に劣り、小さな範囲の詰め物であれば問題ありませんが、大きい範囲を修復しますと、噛み合わせの力により欠けたところや微細な隙間から細菌が入り込みやすく、虫歯が再発しやすくなります。
ここまで、セラミックに関して、万能材質の様なご紹介をしてきましたが、実は気をつけなければいけない特徴があります。
セラミックは強い衝撃で壊れる場合があります。
お皿が割れてしまう状況がイメージしやすいと思いますが、普段は頑丈な素材も、当たり方や当たった先が悪いと破折のリスクはあります。
無理な力で噛んだり、厚みが不十分ですと壊れてしまうので、私たちも十分に留意して日々のセラミック治療にあたっております。
当院では、詰め物、被せ物の必要があったり、ご相談をいただいた際にはカウンセリングを実施しております。それぞれの特徴、費用、治療回数も含め詳しくお話をさせていただいてから治療を行なっております。
気になる方はぜひ、お気軽にご来院、ご相談ください!
2024年08月21日
こんにちは
歯科医師の熊澤です。
年齢が上がるに連れてむし歯や歯周病、歯の破折などが原因で歯を失ってしまうことがあります。
1本なくなっても全然ごはん食べられるよ!問題ないんじゃないか?
と考える方もいらっしゃいますが、本当にそうでしょうか?
今回は歯が少なくなっていく過程をお話しします。
食事を行う際、上下の歯を咬み合わせることで食べ物を細かくしています。
ここで歯が1本減るとしましょう。
①1本減ることでその周りの歯の負担が大きくなる
(例えば3本の歯で負担していたものを2本で負担するため、負担は1.5倍となります)
②負担が大きくなる、周囲の歯が磨きにくくなるなど不都合が生じる
③歯周病や破折のリスクがあがる
④歯を失う
⑤そのままにする
②~⑤を繰り返すことで少しずつ歯を失っていくことになります。
歯を失った際にそのままにしておかずに対応することが重要です。
治療する方法はインプラントやブリッジ、入れ歯などがあります。当院では治療方針についてしっかりお話しした上で治療を行なっていきます。
歯を失ったまま、なんとなく放置している方はいないでしょうか?お気軽にご相談ください。
2024年07月22日
こんにちは、歯科医師の伊藤です。
口ゴボとは、口元が前に突出している状態のことを指します。
具体的には、上あごや下あごの歯並びや骨格が前方に出ているため、横顔から見たときに口元が目立つように見えることです。
口ゴボの原因には、遺伝的要因や、子供の頃の指しゃぶりや舌の癖などが考えられます。
口ゴボは、見た目の問題だけでなく、噛み合わせや発音に影響を与えることもあります。
口ゴボを改善するための治療方法には、歯並びの改善を行う矯正治療や、場合によっては外科手術が含まれることがあります。
外科手術が必要かどうかを決めるのは口ゴボの度合いや歯並びにもよりますが、外科手術をせず歯並びの改善のみを行うカモフラージュ治療といわれる治療法もあります。
カモフラージュ治療とは顎や歯の骨格自体を変更するのではなく、歯並びで見た目を改善するための治療法です。
もちろん、全てカモフラージュ治療を行えるわけではありませんが、お口の中を診断して最適な治療法やどういった方法があるかを相談して治療法を選択することが可能です。
過去に矯正治療は難しいと言われていた方でも当院で歯並び矯正治療を行い、改善し喜んで頂いている方もたくさんいます。
当院では矯正前にレントゲン撮影なども含めて分析して判断しておりますので、口元が気になる方、相談してみたいという方は是非ご連絡ください。
2024年02月19日
こんにちは、歯科医師の大藤です。
突然ですが…だれしも子供のころは乳歯があり、ぐらぐらして抜けて、大人の歯に生え変わってきたと思います。
とはいえ、乳歯のころのこと、覚えていらっしゃいますか?
ご自身もあった経験のはずですが、お子様の乳歯のこと、わからないこと多いですよね。
今回は、意外と知らなれていない乳歯の特徴について、お伝えしようと思います。
乳歯は、番号でいうとABCDEの5番目まであり、上下左右合わせて20本生えます
(もともとない場合やくっついて生える場合もあります)。
生まれる前から顎の骨の中で歯のもとになるタマゴはできていますが、実際に生えてくるのは生後6か月ごろからです。
まず下の1番目の前歯(A)から生え始めます。
10か月ごろに上の前歯(A)が生え始め、1歳ごろには2番目の前歯(B)も出てきます。
1歳6か月ごろに前から4番目(D)の奥歯が生え、2歳ごろに3番目の前歯(C)、2歳6か月ごろに一番奥の歯(E)が生え、すべて生え揃います。
番号でいうと、A→B→D→C→Eが一般的な順番で生えます。
もちろん、順番や時期は個人差がありますので、必ずしもこの順序というわけではありません。
そして、4歳ころから乳歯の根っこが後ろにいる永久歯(大人の歯)に吸収され始め、6歳ころからグラグラし始め、生え変わりが始まります。
乳歯の特徴は、永久歯に比べて歯の長さが短いことや、青白い色をしていることなどがありますが、最も注意しないといけないことは、むし歯になりやすいこと、一度むし歯になると進行が速いことです。
乳歯は、歯を構成している層の厚みが薄く、歯の質自体の硬度が低い(脆い)です。
そのため、砂糖など歯を溶かす作用があるものの摂取回数が多いと、表面が簡単に溶け、あっという間にむし歯になってしまいます。
また、自覚できる症状が不明確で、初期の段階で発見することが難しいという問題もあります。
むし歯になってしまった場合は、まずは削って取り、材料で修復する治療をしますが、進行すると、神経を取る治療が必要になったり、最悪の場合永久歯に影響が出ないように抜歯をしなければならなくなったりすることもあります。
『むし歯になってもいずれ生え変わるんだからいいんじゃない?』と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし…乳歯には大事な役割があります。
もちろん、歯なので食べ物を噛むことができるようになり、栄養素の吸収を助けてくれます。 これだけではありません。
よく噛むことで顎が発達して顔の形も整います。 乳歯があることで舌を正しい位置に置けるようになり、正しい発音の機能も身に付きます。
そして、もう一つ大事な役割として、永久歯の生えてくるスペースを維持するという役割があります。
乳歯がなくなったり、大きく形が変わってしまったりすると、永久歯が生えるスペースが少なくなり、将来歯並びが悪くなったり、それが結果的に顎の発育に影響を及ぼすこともあります。
ネガティブなことも言いましたが…日々のブラッシング、歯医者さんでの定期的な検診を心がけていれば、もちろん予防をすることができます。
いずれ抜けるんだから、と乳歯を軽視するのではなく、大人になるための大切なステップとして日頃からの定期的な予防、早期発見・早期治療をしていきましょう!
何かわからないことや、知りたいことがありましたら気軽にご相談ください。
2024年01月18日
こんにちは、歯科医師の鈴木です。
本日は歯を失ってしまった時の治療法についてご紹介します!
そもそも歯を失わないことが大切ですが、大きなむし歯や歯周病、噛み合わせ、事故や怪我などさまざまな理由によって歯を抜かなくてはいけない場合があります。
歯を失った場合の治療は主に3つです。
①義歯
②ブリッジ
③インプラント
それぞれメリット・デメリットがありますが皆さんがどうなりたいか?によっておすすめするものが変わります。
「見た目が綺麗になりたい」のであれば、
インプラント>ブリッジ>義歯
「歯を削りたくない」のであれば、
インプラント>義歯>ブリッジ
「取り外さないもの」であれば、
インプラント、ブリッジ>義歯
「費用が安いもの」であれば、
義歯>ブリッジ>インプラント
というように患者さん自身が大切にしたいものによって選択肢が変わります。
お口の中の状態や全身の健康状態によっては選択できない場合もあります。
また、歯を抜いたまま放置してしまうと治療自体も難しくなってしまう場合もありますので、もし歯が抜けたままになっている部分がある方は一度早めに歯科医院へ受診して自分に合った治療法の相談を受けることをおすすめします!
当院では患者さんに一人ひとりに合わせた最善の治療を一緒に考えます。お悩みのことがあればぜひお気軽にご相談ください。
2023年10月16日
こんにちは、歯科医師の西澤です。
酷暑も終わり、過ごしやすい季節になりましたね!
紅葉の時期には榛名湖に紅葉狩りにいきたいと思っています!
榛名湖といえば高崎市…
実は!
2023年11月1日に医療法人社団 絆尚会 尾島デンタルクリニックグループ4院目となる
「高崎おとなこども歯科・矯正歯科」が高崎オーパ8Fに開院いたします!
(東京中央美容外科(TCB)様の隣です。)
駅直結の建物なので、電車での通院も便利な立地となっています。
他3院と同様に、矯正治療(インビザラインによるマウスピース矯正を含む)、インプラント、審美歯科、歯周治療、等、同じ治療を行っております。
Instagramでも情報を発信していきますので、是非チェックしてみてください!
絆尚会の各個室は担当者がデザインし、1部屋ずつテーマが違うのですが、今回の高崎オーパ院も絆尚会らしく、今までにないオリジナルのお部屋に仕上がっていますので、高崎に来た際は是非お立ち寄りください!
2023年09月20日
皆さんこんにちは、歯科医師の平形です。
尾島デンタルクリニックが訪問歯科診療を行っていることはご存知でしょうか?
当院では月〜金曜日まで全7チームで訪問診療を行なっています。
もちろんむし歯治療や入れ歯の製作も行いますが、歯科衛生士が口腔機能維持・向上を目指したプロケアも行っています。
外来にいらっしゃって頂くことが難しい方々のご利用なさってる施設やご自宅にお邪魔させていただき、診療しております。
より多くの人のお口の中の機能回復を目指し取り組んで、10年になります。
ただ、訪問歯科診療を行なっている歯科医院は全国的にも20%前後と言われています。
どんなに私たちが強い気持ちで取り組んでいても、実際に訪問診療による歯科治療を希望されている全ての方々のお口を確認するのことは、残念ながら叶いません。
そこで6月30日に、太田商工会議所にて、地域の高齢者利用施設のスタッフの方々やケアマネージャーさんにお声がけさせて頂いて、多職種連携集合研修会を開催させて頂きました。
お忙しいであろう夕方の時間帯にも関わらず、たくさんの方にお集まり頂き、訪問歯科について知って頂くきっかけになっただけではなく、意見交換の場でも積極的にお話頂いて、我々がこれからどんなふうに診療に向き合っていくのか、という新しい形の課題も見つかり、とっても勉強になりました。
ご参加頂きました皆さま、ありがとうございました。
我々が目指している歯科診療は、単に歯科治療を行なってくるのではなく、患者さんの、そして周りのサポートしているご家族や介助者の皆さまのお気持ちに寄り添い、その上で歯科医療従事者として出来る限りのことで関わっていきたい、という形です。
お痛みのある場所やお困りの事を単純に解決するだけに留まらず、患者さんの生活をサポートする一員として仲間に入れて下さったら、嬉しいです。
現在20%と低い割合ではありますが、これからの日本を支える大切な分野と考えおります。
これからも尾島デンタルクリニックの訪問歯科チームは患者さんたちと真摯に向き合い、未来へつながる医療に励んでいくために頑張ってまいります。
訪問歯科診療についてのお問いわせはいつでもお待ちしております。
2023年08月21日
こんにちは、歯科医師の大藤です。
暑い日が続いていますね。夏バテや疲れを感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
疲れが溜まったときに、ふと「痛っ」と感じお口の中を鏡で見ると大きな口内炎が、、、なんて経験をしたことがあるのではないでしょうか?
口内炎があると、お食事が思いっきり楽しめず、つらいですよね。
口内炎は多くの方が経験したことがある疾患です。しかし、一口に口内炎といっても、実ははっきりとした原因は分かっておらず、様々な種類、原因があると言われています。
ビタミン不足や睡眠不足、ストレス、免疫力の低下によるウイルス感染、ホルモンバランスの乱れ、ブラッシングによる損傷や粘膜を傷つけやすい歯並び、なかには服用中の薬剤や全身の疾患によりできるものもあります。
直径0.3~1㎝程度の円形または楕円形で、灰白色または黄白色の膜に覆われ、縁が赤くなって痛みを伴います。
口内炎ができてしまったら、残念ながら治るのを待つことにはなりますが、治りを促してくれる方法をご紹介していきます。こちらは、口内炎の治りを促進してくれますが、もちろん予防にも繋がりますので、まだできていないという方やよくできてしまうという方にも参考になれば幸いです。
まず、口内炎ができるのは頬粘膜や舌、歯茎ですので、粘膜の清潔と強化を意識し、ストレスに負けない身体を作るための栄養を摂取すると良いです。
粘膜の清潔に重要なのは、何よりも日々のブラッシングです。食後や就寝前のブラッシングはもちろん、なるべく毎回隅々まで丁寧なブラッシングを心がけましょう。口内炎ができている部分には刺激が加わらないよう力を入れすぎず、優しく磨きましょう。
粘膜の強化には、栄養素が深くかかわると言われ、中でもビタミン群の摂取が効果的です。特に、ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンCの多い食材が特におすすめです。
・ビタミンA:皮膚や粘膜の健康維持
(含まれる食材)レバー、カボチャ、ニンジンなど
・ビタミンB2:粘膜の保護
(含まれる食材)レバー、ウナギ、納豆、アーモンドなど
・ビタミンB6:皮膚や粘膜を生成
(含まれる食材)カツオ、マグロ、鮭、鶏肉、玄米、バナナなど
・ビタミンC:抗ストレス作用
(含まれる食材)ブロッコリー、柑橘、緑茶など
このほか、口内炎に対する生活習慣のアドバイスとしては、お酒やたばこを控えることや、女性の場合は鉄分の多い食材の摂取を心がけるとより良いです。
歯科医院では塗り薬としてステロイド系の軟膏などを処方することもありますが、自分自身を労わることが予防、治癒への一番の近道です。
いかがでしたか?口内炎ができてしまったら、まずは自分の生活を振り返り、十分な休息を取って、厳しい暑さの夏を乗り越えていきましょう!
2023年06月20日
こんにちは。歯科医師の鈴木です。
みなさん「SDGs」ってご存知ですか?
テレビやインターネットなど、日本だけでなく世界中で進められている取り組みです。
SDGsとは「持続可能な開発目標」を意味し、2015年に国連で採択され、2030年までの国際社会共通の目標になっています。
SDGsでは、17の大きな目標を定め、2030年までの達成を目指しています。
尾島デンタルクリニックは、このSDGsの取り組みを積極的に行っている歯科医院です。
今回は当院で実施しているSDGsの取り組みの一部をご紹介しようと思います!!
■目標1 貧困をなくそう
こちらは世界中で貧しい暮らしをしている人々を助けるという目標です。当院ではこちらの目標達成に向けて様々な募金活動を行っています。最近ではウクライナ募金、トルコ募金など、当院の歯ブラシや歯磨き粉などの物販の売上の一部を募金するという取り組みを行いました。
■目標4 質の高い教育をみんなに
あらゆる人たちが質の高い教育を受けられるようにするという目標です。当院では、セミナーや勉強会への参加を積極的に行うことで日々知識や技術の向上を目指しています。また、小さなお子さまがクリニックの待ち時間に宿題などができるように待合室に学習スペースも設けています。
■目標6 安全な水とトイレを世界中に
■目標14 海の豊かさを守ろう
海などの環境や水という資源を守っていくための目標です。トイレの節水など日常的に資源を無駄にしないことはもちろんですが、地域の環境を守るという観点から当院では月に一度、ド派手な黄色いジャンパーに身を包み、クリニック周辺のゴミ拾い活動も行っています。もし見かけたら手を振っていただけると僕たちもうれしいです!
この他にも17の目標達成に向けて僕たちに出来ることを日々全力で取り組んでいます!
尾島デンタルクリニックのホームページやInstagramでも、SDGsの取り組みについては紹介していますのでぜひご覧ください(^_^)/
2023年05月19日
こんにちは、歯科医師の深谷です。
突然ですが皆さんは何を基準に歯科医院を選んでいますか?
コンビニより数が多い歯科医院。
数が多いと便利ではありますが、良い歯科医院とそうでない歯科医院の見分けがつけにくく、
どこを選べばよいかわからなくなりますよね。
業界のタブーとも言えるこんな疑問について僕の考えを率直にお伝えできたらと思います。
治療が上手い、先生が優しい、患者数が多い、最新の設備がある、消毒滅菌がしっかりしている、医科の先生との連携、ホームページやカウンセリングが充実している、家から近い等、
良い歯科医院の指標は沢山あります。
ですが、選択する皆さんからすれば、指標が沢山ありすぎると
どこが良い歯科医院かわかりにくいと思います。
食や見た目を通じて人生に大きな影響を与える歯科医院選び。
このBlogを通してなるべく多くの皆さんが良い歯科医院に出会えることを願っています。
その中で、実際に歯科医師として歯科医院で働く私が最も重要だと感じ、
これをおさえておけば間違いないと思う指標をお伝えします。
それは、スタッフの定着率!!!
実際に内部で働くスタッフは、良いことも悪いことも全て知っています。
設備やホームページは充実していても先生がいい加減な治療をしているような歯科医院には、
スタッフは定着しません。
当院は新卒3年目のスタッフの定着率が100%です。
この数字が全てを表しています。
結婚や出産などで一時的に職場を離れるスタッフもいますが、
皆復帰して活躍してくれています。
その理由は、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保育士、管理栄養士、歯科助手等、
全職種が、常に患者さんに最良な治療を提供するために働いているからに他なりません。
全職種が仕事に誇りを持ちそれぞれの役割を果たしています。
その結果として、新卒3年目スタッフの定着率が100%を達成し、
多くの患者さんが当院を選んで通院して下さっています。
また、スタッフのご家族の方々も当院を選んで通院して下さっています。
当院はスタッフがご家族に自信をもって紹介できる歯科医院です。
通院するたびにスタッフが入れ替わっている、
ホームページにうつっていないスタッフばかりいる、
スタッフの表情が暗い等の歯科医院は少し注意が必要かもしれません。
当院は治療が上手い、最新の設備がある等のことは当然として、
患者さん一人一人に合わせた最善の治療を提供しています。
今後歯科医院選びに困った際には、是非参考にしてみて下さい。